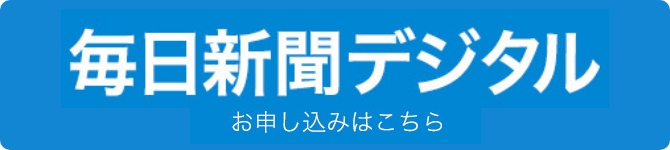2023.05.31
テレビが怖いから、学童に行きたくない|せんさいなぼくは、小学生になれないの?⑦
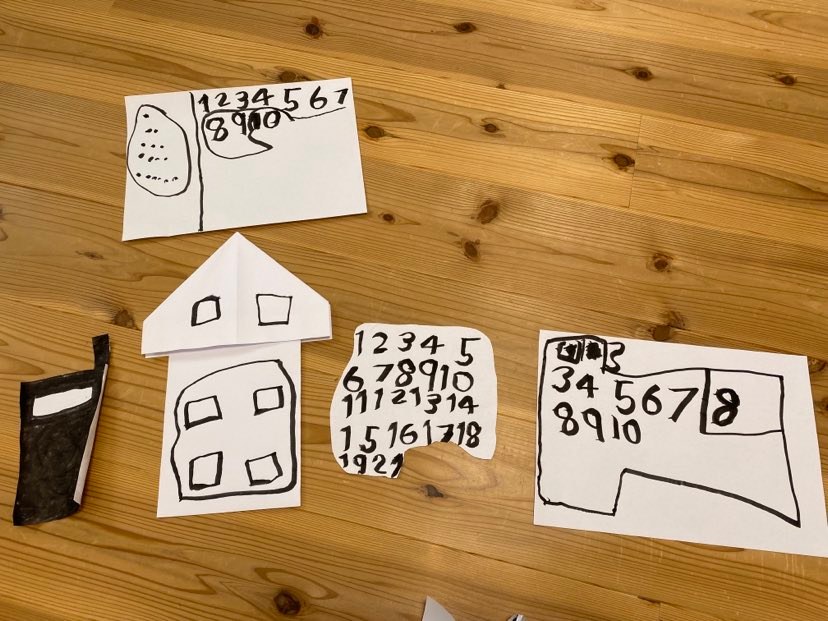
「朝の競争をやりたくない」 「学校に行きたくない」
むすこは朝起きると気持ちを強く主張するようになった。
「学校の何がいやなの?」 そう聞くと、 「学童のテレビが怖い……」 と言う。
むすこの学童は、小学校のグラウンド脇のこじんまりとしたプレハブ小屋にある。
我が家は夫婦共働きのため、入学前の4月1日から学童を使っていた。1年生は、入学後も午前授業が多い。むすこは学校が終わってから夕方まで、学童で過ごしていた。
その時間が、むすこにとって苦痛で、集団生活を送る上での「ひっかかり」になっているようだった。 特に、テレビがいやだ、と繰り返し伝えてきた。その学童では長期休みなどでお弁当を持参する日は、食後に30分〜1時間ほどアニメのDVDを見せている。むすこは、その内容が怖いと言う。
流されるのは、子どもたちに「人気」のアニメばかりだ。むすこには、時々出てくる戦いのシーンや、不安をかき立てるシーンなどが怖いようだった。家でも、アニメはおさるのジョージや、ムーミンくらいしか見ようとしない。それらもウイルスや、お化けなど「怖い要素」が登場すると、途中で見るのをやめる。
そもそも学童でDVDを見せるのはどうなのだろうか、とも思う。むすこがテレビをとても怖がることなどから、その時間だけ別の場所で見守ってもらえないか、と入学前から相談していた。
だが「子どもたちの食後のお腹休めと、職員の打ち合わせ時間が必要」と、別の場所で過ごすことはかなわなかった。むすこはその間、DVDを見ている子どもたちと同じ室内の、映像が見えない場所で職員さんと過ごすことになった。
でも、その場所はカーテンで仕切られているだけで「音が聞こえて怖い」と言う。注:むすこは「HSC(Highly Sensitive Child、ひといちばい敏感な子ども)」と呼ばれる性格特性を持っている(注:現時点では診断は受けておらず、医師と相談中)。最近、話題になることが増えた「繊細さん」=「HSP(Highly Sensitive Person、ひといちばい敏感な人)」の子ども版だ。 ▼においや音に敏感▼新しいことをはじめる前に、とても時間をかけて観察する▼人前で話すのがとても苦手 などの特徴がある。 HSCの子どもにとって、怖い映像への恐怖感は、大人の想像以上であるようだ。このときは、HSCという概念を知らなかったため、学童側に配慮を強く求めなかった。後日、市議会議員を通して、役所の担当課長に聞いてもらったところ、「DVD視聴は疑問を感じるので、実態を調べてみる」との回答があった。
学童の環境も幼稚園とは違い、教育や保育の専門資格を持たない職員さんも多いようだ。「子どもの主体性や気持ちを尊重する」というより、決められた時間に、決められたことを子どもにやらせている。
学童を利用しはじめたときのむすこの感想が象徴的だった。
「折り紙は1枚しか使わせてもらえない」 「グラウンドは遊んじゃだめなんだって」子どもの主体性や気持ちを重視する幼稚園で育ったむすこにとっては制約が多く、きゅうくつに感じられるのかもしれない。(もちろん職員さんはそれぞれ職責を果たしているし、良い方が多い。ただ、繊細なむすこの言動に想像が及ばないようだった)。
******
しぶしぶ家を出て、集団登校の列に加わっても、 むすこの「行きたくない」は止まらなかった。
集団登校という一斉に動かなければいけない登校方法もむすこにはプレッシャーなのかもしれない。
注:集団登校に無理に参加させるより、学校に事情を説明して自分のペースで登校できるようにしたほうがよかったと今は思う。
近所の1年生のなかには、親が集合場所までついてこなくなった子もちらほら。むすこは早生まれで、その子たちとは1歳近く年が離れているとはいえ、その姿がまぶしく見える。
むすこが母の手をずっと離さないので、手を引き離す。だが、その場から全く動かない。仕方なく、ぼくは20キロ近くになった体を抱きかかえて、約1キロの坂の多い道のりを歩く。マスクをしながら歩くので、はあはあ息が上がる。なんとか学校の目の前にある陸橋まではたどりつき、そこからは手をつないで歩く。
学校の玄関で同じ登校班の友達が待っていてくれた。でも、むすこは「行かない」と、下駄箱のところで動かない。 教室におんぶで向かう。 廊下で、保健室に向かう担任の先生とすれ違う。 「振り出しに戻ってしまいました……」 とぼくは言う。 教室に到着。 ランドセルからむすこの代わりに荷物を出す。手洗いに行くと、同じ幼稚園出身の仲の良い女の子たちが 「がんばって」 「かわいいね(赤ちゃんみたいにしているからか……)」 と手を引いてくれるが、むすこは手洗いをしない。
教室に戻ると、先生に「今日はだっこだったんですね」と声をかけられる。「疲れたのでしょうか。学童に行きたくないと言っていて。週末は、剣道や、ボーイスカウトの体験会に参加して楽しそうにしてたんですが」
「参加したんだ。それはよかったね!」と先生はむすこに声をかけるが、むすこは終始うつむきかげんだった。
1時間目は音楽で、音楽室へ移動。ぼくはむすこの席の横にしゃがんで付き添う。 先生はCDをかけて、子どもたちに何の歌かを問いかける。「♪小鳥はとっても歌がすき……」 「♪ちょうちょう、ちょうちょう……」 「♪黒やぎさんたら……」
おなじみの童謡だ。 次は、タララララーと、前奏が長めに流れてくる。
「この歌は、何でしょう?」と先生が聞く。 「はい!」 「はい!」 クラスの半分ほどが手をあげる。 「何ですか?」 先生が続けて聞くが、誰も答えない。 手をあげているだけで、 実は誰もわかっていないのだ。 1年生のかわいらしさに、ついほほ笑んでしまう。 もう少し前奏が流れ、 「♪さいた、さいた、チューリップの花が」 と歌まで流れて、 「チューリップ!」という声がようやくあがる。 8時半、8時40分……といたずらに時間が流れていく。ぼくはじりじり焦りはじめる。
「時計の長い針が6になったら教室を出るね」と約束しようとするが、ぼくが席を離れようとするとくっついてくる。足をすり寄せてくる。
1時間目の途中で音楽室から教室に戻り、算数の時間になる。
休み時間に、担任の先生と少し話す。 「どれくらい付き添いをしたほうがいいものでしょうか?」 「本人が納得して、離れられるようになるまで、ですかねえ。昨年も1年くらい付き添いのあった子もいます。親が離れると、それで切り替わる子もいますし。○○くんの場合は、一人になっても明るくならないところが気になるところです……。『何時にお父さんと別れる』とか、約束できるといいのですが」「先週までは、今日は途中まで一緒に来て、明日からは一人で登校する約束だったんですがね……」
はあ。振り出しに戻っているなあ。注:むすこが教室で明るくならないのは、教室環境への基礎的な安心感がないからで、本来の明るさが出ないほど教室に強い不安や恐怖感があったことに気づいてあげられていたら、と今は反省している。
「がんばりなさい」と何度もむすこの手を振り払っても、
「仕事があるから行かなくちゃいけないんだ」 と強い口調で言い聞かせても、何をしてもぼくから離れない。むすこは、うっすら涙目になっていた。
【書き手】沢木ラクダ(さわき・らくだ) 異文化理解を主なテーマとする、ノンフィクションライター、編集者、絵本作家。出版社勤務を経て独立。小さな出版社を仲間と営む。ラクダ似の本好き&酒呑み。
【我が家の家族構成】むすこの父である筆者(執筆当時40歳)は、本づくりや取材執筆活動を行っている。取材や打ち合わせがなければ自宅で働き、料理以外の家事を主に担当。妻(40歳)は教育関係者。9時~17時に近い働き方で、職場に出勤することが多い。寡黙で優しい小1の長男(6歳)と、おしゃべりで陽気な保育園児の次男(3歳)の4人家族。