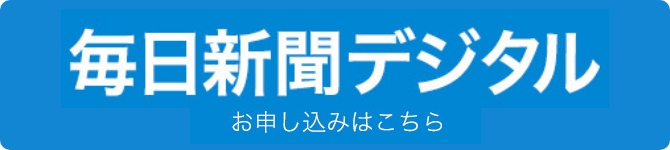2025.03.07
「キャンペーンガールは役割終えた」 広告のプロが断言する背景

企業の宣伝を担ったキャンペーンガールが繊維やビールの主要各社から姿を消した。消費者が多様化し、若い女性の姿で注目を集める広告に疑問を持つ人も増えている。広告主企業でつくる業界団体「日本アドバタイザーズ協会(JAA)」の幼方聡子・サステナビリティ・コミュニケーション委員長(東レインターナショナル、広報・マーケティング支援室長)に広告のあり方などを聞いた。【聞き手・久野洋】
――多くの企業がキャンペーンガールを起用しました。
◆私がいる繊維メーカーでいうと、水着素材の販売促進が目的でした。売り場のイベントでお客様に水着のトレンドを紹介し、水着アパレルとともに流行を作ってきました。消費者との直接の接点が少ない繊維メーカーにとって、キャンペーンガールは企業の知名度やイメージの向上にも貢献しました。
2000年代以降、海水浴人口の減少で水着市場が縮小し、加えてインターネット通販やSNS(ネット交流サービス)も普及しました。水着素材の販促を目的としたキャンペーンガールは役割を終えました。イメージ戦略でキャンペーンガールを残す企業もありましたが、事業多角化や海外進出が進み、キャンペーンガールで会社を表現するのも難しくなりました。
――女性の姿で注目を集める手法への逆風が強まりました。
◆もともと広告に登場する性別でいうと、圧倒的に女性が多いという歴史がありました。女性を起用するほうが商品をアピールしやすいと考える企業が多かったのだと思います。
今、広告の受け手の価値観が多様化しており、それを発信側も理解する必要があります。多くの企業は、映画やドラマ、広告の中で描かれるジェンダー表現が社会にどう影響するか、意識しています。漫然と女性を起用するのではなく、どうしてその表現となったのか、合理的な説明が求められます。
――広告による『炎上』も起きやすいです。
◆企業の広告担当者間で勉強をしていますが、炎上は関心の高いテーマです。広告を目にするのは商品のターゲット層だけではありません。多様性に配慮し、全ての人を取り残さない表現を模索しています。
一方で、ジェンダーバイアス(性別に基づく固定観念)に過剰に配慮した表現にすると、逆に不自然な印象を抱かれるとの調査結果もあります。印象に残る演出と多様性への配慮の両立を多くの企業が模索しています。炎上を防ぐことは大切ですが、炎上した際に責任を持って説明できるかどうかも企業の姿勢が問われるポイントです。
関連記事