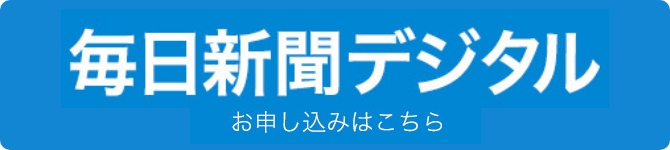2025.03.25
「棚を埋めたい」 コメ高騰、集荷競争も要因か JA全農部長の見方

収束が見通せないコメの価格高騰。さまざまな議論が続く中、JAの経済事業を担う連合体で、日本最大の集荷団体でもあるJA全農(全国農業協同組合連合会)の藤井暁・米穀部長に話を聞く。【聞き手・三枝泰一】
シリーズ「令和のコメ騒動」5
――集荷の最前線を統括する立場で、現状をどうみますか。コメを投機対象にした事業者が抱え込んでいるのでは、という声も聞こえてきます。
◆昨年の夏の品薄に危機感を抱いた小売りから卸までの幅広い事業者が産地に集荷に入り、コメの流通が細かく分散したというのが実態ではないかと考えています。
――その「品薄」の要因は?
◆2023年産米は猛暑の影響で1等米比率が61・8%となり過去約20年間で最低でした。結果、品薄が表面化する直前の24年6月時点で、コメの民間在庫量は前年同期と比べ44万トン少なくなりました。具体的には197万トンが153万トンになりました。
全農の試算では、同時期の2人以上の世帯のコメ消費量は前年比101・1%と堅調に推移し、家庭用需要が5万トン増加したものと考えられます。コロナ禍の収束で業務用(中・外食)も同104・6%と回復。需要が10万トン増えた計算です。
そこに、特殊要因として8月の南海トラフ地震臨時情報の警戒や台風接近情報が加わったことで、主に都市部のスーパーの販売数量が急伸し、精米商品が無くなる現象が起きました。8月下旬から9月下旬までに出荷された24年産米の卸への出荷量は、前年比200%超と前年を大幅に上回る状況になりました。
――集荷競争が始まった。
◆早期に棚を埋めたい小売りが、さまざまなつてをたどって産地にオファーする動きが起きたと考えています。
――つまり「実需」のある動きだったと?
◆さまざまな原因が重なったと考えられますが、そのうちの一つだったと思われます。
――今後の需給見通しは?
◆1月の農水省の食糧部会で、昨年6月末時点で153万トン、今年6月末時点では158万トンと試算されています。25年産米については、国が設定した目安通りになれば、来年6月末には178万トンに回復する見通しです。
――昨年成立した改正農業基本法は、持続的な食料供給に向けて、食料価格は「合理的な費用が考慮されるようにしなければならない」という考えが盛り込まれました。消費者が気をもむのはコメの販売価格です。食料価格全般の高騰で、昨年のエンゲル係数(家計に占める食費の割合)は1981年以来、43年ぶりの高い水準になりました。今年2月の東京都区部のコシヒカリ(5キロ)の価格は4368円で前年同月の1・8倍に跳ね上がっています。コシヒカリやあきたこまちの1俵当たりの卸間価格は5万円前後で、1年前の3倍の価格帯で推移しています。
◆行き過ぎた価格高騰は、営農の安定化にプラスには働かないと考えています。基幹的農業従事者(自営農業)の数は18年間で約100万人減り、1人の農業従事者の食料供給で支える日本人の数は、2010年の62・4人から20年には92・5人に増えた計算になります。肥料など資材の高騰で生産費が上昇しており、このままでは生産が維持できなくなるのでは、と危惧しています。一方で、極端に価格が上昇するとコメ以外の食品に消費が移り、コメ需要の減少が懸念されます。
このような需給環境で適正価格の具体的な額を言うのは非常に難しいのですが、生産者と消費者が互いのことを思い、継続的な生産と消費ができる水準を目指していくことが重要だと考えます。
――生産調整をやめ、増産したコメの輸出を視野に入れる考え方については?
◆国内の人口減少を考えれば、輸出は増やしていくべきだと考えます。日本のコメをおいしく食べてもらうためには、日本の食文化を同時に発信することも重要です。「パックご飯」や日本酒のようなコメの加工商品を含めて、相手国の需要に応じた輸出を行うことが大切です。
ふじい・さとる
1972年、埼玉県生まれ。95年、慶応大卒。2024年から現職。
関連記事