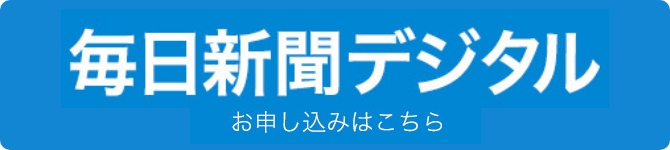2025.04.03
水を治める 先人たちの決意と熱意、技術に学ぶ 戦国城にみる液状化現象 連載64回 緒方英樹
目に見えない地盤の上で暮らすということ
埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故では、私たちの暮らす舗装された道路やコンクリート地面の下には軟弱な地盤があり、その中に重要なインフラがあることを改めて思い知らされました。
地盤とは建物など構造物の基礎を支える地面のことです。私たちはその地盤の下にインフラを張り巡らして生活しているわけですが、地盤の状態や土地の高低は災害リスクに大きく影響していると言えるでしょう。

そして、今回取り上げる液状化現象は、緩く堆積(たいせき)した砂の地盤に強い地震動が加わると、地層自体が液体状になる現象のことです。
液状化は、地震発生時に起こる可能性がある被害です。地面に水分がたくさん含まれているような場所、たとえば海岸や川の近く、埋め立て地、砂丘や砂州の間の低地などが挙げられますが、条件を満たせば内陸の平野部でも発生します。
ひとたび液状化が起こると、砂の粒子が地下水の中に浮かんだ状態になり、地盤が沈み始めて、地下の埋設物が損壊、建物が傾斜・沈下してしまいます。道路やライフラインの災害など、都市型災害としても大きな影響を国民生活に及ぼしやすい危険性をはらんでいます。
この予兆は、今から400年以上前、歴史を大きく動かした転換期にも見られます。
琵琶湖畔に築かれた幻の名城たち

琵琶湖は、古代より畿内から東海、北陸への交通の要衝として、戦国時代、琵琶湖の周辺には多くの城が築かれました。
1579(天正7)年、織田信長は石垣や瓦による安土城を築きます。東国から都に入る交通の要衝となる安土の築城は、領国全体を俯瞰(ふかん)できる絶好スタンスの確保でもあったことでしょう。北陸と近畿のほぼ中間点に位置する琵琶湖は、人や物が行き交う非常に重要な交通のポイントだったのです。そして、琵琶湖東岸のほぼ中間点への立地は、湖を利用した湖上交通という最大の優位がもたらされる。信長の地選にはそうした目論見(もくろみ)があったと思われます。
その琵琶湖畔には、安土城をはじめ明智光秀が築いた坂本城、秀吉が長らく居城としてきた長浜城など琵琶湖ネットワークが形成されていきました。
秀吉と家康の運命を変えた天正の大地震
戦国時代は、大地震が連続して発生した時期とも重なり、大地震が大名や武将、庶民たちの運命を狂わせていきました。その中でも、1586(天正13)年に発生した天正地震は活断層による直下型の大地震と言われています。震源域は近畿地方から東海・北陸地方の広範囲に渡っていました。当時の文献をみると液状化現象も起こっていたようです。

豊臣秀吉と徳川家康との小牧・長久手の戦いは天正12 (1584)年ですから、そんな激動の時代に近畿、東海、北陸にかけて襲った起きた天正地震は、まず秀吉の運命を揺り動かしました。
地震が発生したとき、秀吉は家康討伐準備のため大垣城を訪れた後、琵琶湖畔の坂本城(滋賀県大津市)に立ち寄っていました。ちょうど秀吉による天下統一がほぼ終わった頃、坂本城で大地震にあった秀吉は、大いに肝を潰したことでしょう。ポルトガルから来た宣教師ルイス・フロイスによると「関白は、かつて明智の近江の湖のほとりの坂本の城にいた。だが彼は、その時に手がけていたいっさいを放棄し、馬を乗り継ぎ、飛ぶようにして大坂へ避難した」と著書「日本史」に記しています。
さらに、秀吉が長らく居城としてきた琵琶湖畔の長浜城も、地震の震源地に近かったこともあり液状化現象による大惨事を受けました。当時の宣教師などの記録によれば、城下町は倒壊し、火事が発生して家々の半分は焼失、ほぼ全壊してしまいました。城主を務めていた山内一豊は、地震で倒壊した棟木の下敷きになって一人娘を失いました。

秀吉は、当時家康への攻撃を計画していましたが、地震で前線基地を予定していた大垣城を失い、さらに戦で先鋒を担うはずだった山内一豊の悲しみは、禅宗に帰依する程深く、秀吉は家康討伐を断念して和解します。大地震が歴史を変えた一例と言えるでしょう。
大渇水が蘇らせた幻の城跡
琵琶湖の南湖西側に位置する坂本城は、1571(元亀2)年、比叡山焼き討ちの直後に、織田信長の命により明智光秀が坂本城を築いた幻の名城です。城内には琵琶湖の水が引き入れられており、城内から直接船に乗り込み、そのまま安土城に向かったようです。従って城郭の建物が湖水に接した「水城(すいじょう)」形式の城と推定されます。
しかし、本能寺の変後、光秀が山崎の戦いで最期を遂げた後、築城から約15年で坂本城は廃城となっていました。その後、2021年、琵琶湖の水位が低下したことにより、普段は湖底に沈む石垣が姿を現して人々を驚かせました。発掘調査では、10~30センチの焼土層が発見されました。これは明智秀満が天守に火を放ち光秀の妻子もろとも落城した時のものと考えられています。

徳川家康の清洲越しは、高台移転
天正地震で液状化の被災を受けたとされるのが尾張の清州城です。
若き信長の本拠地、後に清須会議の舞台となった尾張の中心地・清洲ですが、低地に位置し、水害への不安にさいなまれていた地域で、加えて一帯は軟弱な地盤だったことから、大地震に伴って液状化現象が起きたとされています。この時の液状化の痕跡を示す地層は切り出され、名古屋大減災館(名古屋市千種区)で「剥ぎとり展示」として公開されています。
この経験を教訓として、江戸時代の初め、高台・名古屋へ集団移転を断行したのが徳川家康です。清洲から城下町ごと熱田台地の北西端に高台移転をした名古屋への大引っ越しは「清洲越し」と呼ばれています。
徳川家康による「清洲越し」が完了したのは1613(慶長18)年、当時「思いがけない名古屋ができて、花の清洲は野となろう」という歌が残っています。
自然災害と人間の叡智、そこにあるのは天地(あめつち)に向けた篤実な姿勢にあるのかもしれません。継承されていたことに深く心を打たれます。