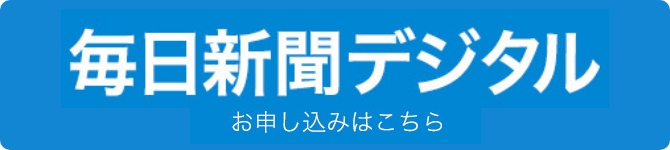2025.04.24
「どこでも行きまっせ」 吃音を克服した福祉落語家、高座1万席達成

阪神大震災をきっかけに高齢者らに笑いを届け続ける福祉落語家、壽文寿(ことぶきもんじゅ)さん(63)=兵庫県尼崎市=が、落語界では偉業とされる高座1万席を達成した。初高座から51年11カ月。吃音(きつおん)を落語で克服した。小さな高座を大切にして、達成後も記録を更新し続ける文寿さんは「まだまだ、頼まれる限りはやらしてもらいます。どこでも行きまっせ」と意気盛んだ。【桜井由紀治】
4月19日、神戸市兵庫区の東出町自治会館。テーブルを並べた特設の高座に文寿さんの姿があった。町自治会主催の「介護予防サロン」。地域のお年寄り約30人を前に、文寿さんはよく通る声で語り始めた。「お客さんも十人十色。よく笑う人、なかなか笑わない人、笑いをこらえる人。一番嫌なお客さんは、家に帰ってから笑う人」。会場は笑いに包まれる。1万146席目の高座。この日は同県猪名川町でも出演した。
文寿さんはこうした“ミニ高座”を精力的にこなし2024年11月17日、京都府宇治市で開催された「天岩戸開き寄席」で通算1万席を達成した。
小3の頃、自身の吃音を差別した担任教師の発言をきっかけに、同級生からいじめを受け、7カ月にわたって不登校になった。日中に街をさまよい歩き、補導歴も数回ある。
不登校中、祖母とともにラジオで聞いた落語に強い興味を持ち、積極的に話すことで吃音を克服しようと、東京の寄席を訪ねた際に声をかけてくれた橘右近師匠(故人)に師事して修業を始めた。
1972年12月、初高座を務めた。この頃はまだ吃音はあったが、懸命に話すと観客は笑ってくれた。それが大きな自信となり、その後も高座に上がり続け、約18年かけて吃音を克服した。
転機になったのは95年の阪神大震災。仮設住宅では高齢者の孤独死やアルコール中毒が問題となっていた。被災者を笑いで元気にしたい。46カ所の仮設住宅集会所を回り、ボランティア落語会を開催した。
仮設住宅を視察に来ていた兵庫県職員の目に留まった。健康をテーマにしたネタが高評価され、98年4月に県公認の福祉落語家を“襲名”した。老人ホームや病院、障害者施設、公民館などで落語をするようになった。
出演料は主催者の予算に合わせる。「福祉落語家を名乗る限りは、お金のことを言うたらあきまへん」。ネタは還付金詐欺の防止策や、笑いの健康効果など高齢者を意識した話を枕にする。
評判は口コミで広がり、県内外から出演依頼がかかる。ほとんどが小規模施設や小さな催しだが、呼ばれたらどこでも行くという。
吃音に悩んだ経験から、同じ障害で悩む子どもを勇気づけたいと地元・尼崎市内の小学校でも演じる。家に閉じこもりがちな高齢者宅を訪ねる「出前落語」も始めた。
弟子入りしたとき、師匠からは「2000席を目標にしなさい。それだけ続ければ吃音も克服できるだろう。つらくても精進しろよ」と励まされたという。気づけば目標の5倍の高座数に。「私の落語を聞いて笑ってくださるお客さんのおかげ。これからも一席一席を大切にして、全力投球でしゃべっていきたい」と抱負を語る。出演依頼はメール(monju-frn@ezweb.ne.jp)で。
30日午後1時半から、神戸市兵庫区水木通2の中山記念会館で1万席達成記念の落語会がある。無料。定員60人。申し込みは、主催のNPO法人神戸アイライト協会(078・531・6340)。
関連記事