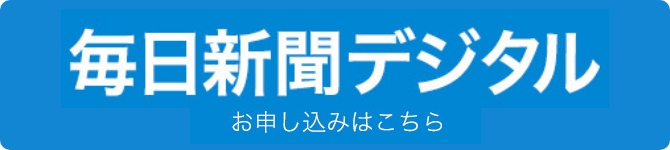2025.05.28
水質をものともせず 生命力にあふれ生き生き泳ぐ大群「ボラクーダ」
「光化学スモッグ注意報」を示す黄色い掲示板を覚えている世代は、「ボラ」に対して良い印象がないかもしれません。公害の影響が残っていた時代背景と、苦しげなボラの表情が重なってしまうのです。都市部の濁った川や運河、港湾の岸壁に集団で押し寄せて水面で口をパクパクさせ、釣り上げて持ち帰っても小骨が多く調理しにくいうえ、臭くて食べられない……というもの。
◇
でもボラは、刺し身、塩焼き、鍋料理など重要なたんぱく源として、古くから日本人に親しまれてきました。メスの成熟した卵巣は、日本の三大珍味のひとつ「カラスミ」の原料として珍重されています。
この違いは、どこからくるのでしょう。
ボラは雑食性で、石などに付着した藻類のほか「デトリタス」と呼ぶ生物の死骸や排せつ物、微生物が海底に沈んで微粒状になったものを、泥と一緒に食べています。海底を浄化する役割を担っているわけです。
ところが、ヒトの活動により水質が悪化して自然に浄化できる限度を超えると、沈んだ有機物は腐って臭気の漂うヘドロになります。そのせいで、それらを食べるボラも異臭を放つのです。淡水や汽水域にも入り込み、水質汚染に強く生活排水が流れる水路ですら生きていけるボラの強さが、逆に災いになったのです。ボラに「罪」はありません。
また、化学物質や有機物による水質の悪化はプランクトンの増殖を招き、水中の酸素を激減させます。ボラが水面で口をパクパクさせていたのも、水中に溶け込む酸素が少なかったからです。
本来、清らかな海から水揚げされたボラは、淡泊で上品な味です。冬に脂がのった「寒ボラ」は特においしいらしく、マダイにも劣らないとのこと。私が鍋料理で食べた時には、タネ明かしをされるまでボラとは気づきませんでした。あっさりして、もみじおろしのポン酢で食べるのが、よいあんばいでした。
一方、今も冬の終わりから春にかけ、全国各地の海や川にボラの大群がやってきてニュースになることがあります。これは、詳しい理由はわかっていないものの、成長過程で水温の変化が理由だったりエサを探したりする一般的な習性で、環境悪化とは関係がなさそうです。
写真を撮影した高知県の柏島には、ほぼ毎年5月の数日間、大群が回遊してきます。地元では、春の風物詩として「春ボラ」や「ボラなぶら(魚が跳びはね海面がざわつく様子)」と呼んでいます。
ダイバーは、太平洋の熱帯域で人気が高い大型のカマス「バラクーダ」になぞらえ、この大群を「ボラクーダ」と称して歓迎します。このボラたちは、生命力にあふれ生き生きと泳いでいます。かつて私が見た、口をパクパクさせるボラと同じ種類とは思えません。
柏島の海は数年前、空中に浮かぶようなボートの写真がSNS(交流サイト)で拡散され、透明度の高さが全国に知れ渡りました。私が公害の時代に過ごした都市部の海とは雲泥の差です。このボラたちは美味に違いありません。(高知県大月町で撮影)【三村政司】
関連記事