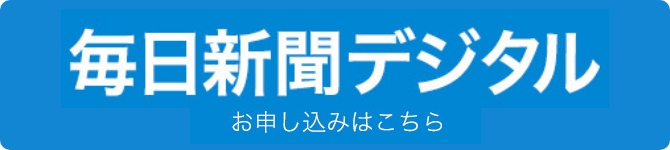2025.06.09
実はしたたか? 天気で花が向きを変えるメカニズム解明 京大チーム

晴れた日には顔を上げ、雨天では下を向く。アブラナ科の多年草「ハクサンハタザオ」が天候によって花の向きを変えるメカニズムを明らかにしたと、京都大生態学研究センターの研究チームが発表した。こうした植物の現象を解明したのは初めてで、生き残るための植物のしたたかな戦略があることも分かった。研究成果は英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された。
研究チームは2022~23年に兵庫県多可町で野外調査を実施。光が強く気温が高い時は花が上向き、雨天や夜には下向きだった。このことから、花の向きは光や温度、1日の生活リズムを作る「体内時計」などが関係していることが予測された。
次に、人工的に光や温度、湿度などを変化させ、花の向きを変える要因を絞り込んだ。その結果、昼の時間帯に温度がある程度高い場合、花が青い光の方向を向くことが分かった。植物は光に向かって成長する「光屈性」という仕組みを備えており、青色光に反応したと考えられる。
一方、光が少ない雨天時の茎からは、細胞の成長に影響する植物ホルモンを多く検出。重力を感じて伸びる向きを決める「重力屈性」によって花が下を向くことが分かった。
では、なぜ光によって花の向きが変わるのか。チームは、花のすぐ下の茎「花柄(かへい)」を上側と下側に分け、植物の成長を促進するホルモン「オーキシン」に関連する遺伝子が発現する量を比較。青い光を当てると、下側で発現が高まり、花を上向きにしていた。逆に青い光が少ないと、上側の発現が多くなり、下を向いていた。
さらに、この仕組みがハクサンハタザオに何をもたらすのかを調べるため、人工的に上向きや下向きにした花を雨にさらした。すると、下向きの花の方が花粉の流出を抑えられ、花粉の保護につながっていた。
また、両者を晴天時に昆虫のいる環境に置くと、上向きの花の方がたくさんの虫を引き寄せ、より多く受粉に成功して実をつけた。
京都大生態学研究センターの元研究員で福井市自然史博物館の柴田あかり学芸員は「自然がいかにうまく機能しているのかが実験によって明らかになった。メカニズム研究と実験を組み合わせて、植物の興味深い特性を調べていきたい」と話している。【田中韻】
関連記事