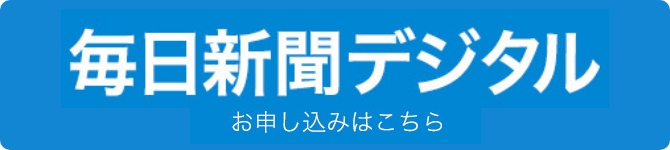2025.07.25
女性の不安あおる商品に危機感 若手研究者らがGI考えるグループ

身の回りのものやサービスが男性のデータを基準に作られ、女性らが不利益を被る「見えない性差」の存在が近年認識されるようになってきた。
「ジェンダード・イノベーション(GI)」は、この課題に性別や多様性の視点を取り入れることで、より公平な研究開発を進める概念だ。
日本でも少しずつ知られるようになってきたが、政策や研究現場での取り組みは遅れている。こうした現状を変えようと若手研究者らが立ち上がった。
東京大大学院情報学環・学際情報学府の大学院生、江連千佳さん(24)らは昨年11月、若手研究者らがGIについて学び、交流するグループ「Blend(ブレンド)」を設立した。
GIは2005年に米スタンフォード大のロンダ・シービンガー教授が提唱し、欧米を中心に浸透してきた。病気の診断や薬の用量、自動車の安全性テストなどがGIの視点で分析され、女性だけでなく男性についてもリスクの改善や、技術革新につながっている。
欧州連合(EU)は、21年から研究費の助成を申請する際に生物学的な性差やジェンダーの視点を含めることを必須とした。また、学術誌ネイチャーと関連誌は22年、論文の投稿で性別やジェンダーについての考慮の有無や内容を報告することを求めている。
日本でも23年、性差の視点を踏まえた研究を促進するよう、国の競争的研究費の指針に明記された。また、6月に閣議決定された女性活躍に向けた政府の重点方針「女性版骨太の方針2025」にも、前年に続きGIの推進が掲げられたが、政策などの具体的な取り組みはこれからだ。
江連さんは、22年にお茶の水女子大にGI研究所ができたことでこの概念を知った。
「こんなに面白い考え方があるんだ」。江連さんは、女性の健康課題や悩みを改善する「フェムテック」にかかわる分野で起業していたこともあり、近しいものを感じた。
一方で、江連さんは日本でGIより先に浸透した「フェムテック」に危うさも感じていた。「『デリケートゾーンをケアしないと女性としての魅力が落ちる』と不安をあおる商品など、『女性のため』をうたいながら、本当に女性のためになっているのか疑問に感じるものも多かった」。
そんな時に、科学的根拠に基づいて性差を考慮した研究開発を進めるGIの存在を知った。
そして一部のフェムテック商品やサービスを批判的に研究して整理し、よりよいものにしたいと思い、東大大学院に進学。東大やお茶の水女子大の学生らとともにGIのグループを設立した。
Blendの名前の由来は「ブレンドコーヒー」。多様な視点が交わり、新たな発見やアイデアを生む場にしたいとの思いを込めた。
文系、理系を問わず、GIに関心を持つ学生や若手研究者十数人が集まり、月に1度、それぞれの研究や分野に応用する方法について意見交換している。
江連さんは、GIが単に研究だけでなく、それを担う人材の育成や社会全体の環境づくりにも焦点を当てていることが重要だと感じている。
科学技術の発展から女性が排除されてきた歴史を見直さないまま、爆発的な人工知能(AI)技術の発展といった技術革新が進めば、格差がさらに拡大してしまうことも懸念する。
「今誰かが止めないと、次の世代に格差が残ってしまう。公正な未来のために学術と産業界をつなぐ道を作っていきたい」と意欲を語る。【中村好見】
関連記事