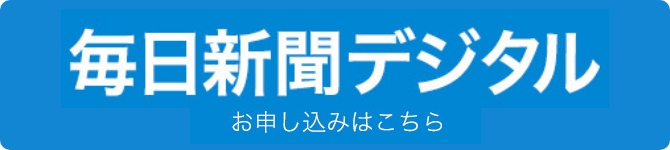2025.07.29
目指すは治水推進と減災 教訓胸に官民一体で備え 第20回水害サミット

水害などを経験した全国の地方自治体のトップが対策などについて意見交換する「第20回水害サミット」(同実行委員会、毎日新聞社主催)が6月3日、東京都千代田区のパレスサイドビルで開かれた。
第1部は「持続可能な地域社会の実現と流域治水の推進」、第2部は「命を守る避難情報の発信と防災DX(デジタルトランスフォーメーション)による効率的な災害対応の実現」をテーマに、19道県30自治体の首長と中野洋昌・国土交通相・水循環政策担当相が参加。事例発表と真剣な議論が交わされた。
【コーディネーターは元村有希子・毎日新聞客員編集委員、構成・猪狩淳一、山内真弓、篠崎真理子】
実行委員会代表のあいさつ 白岩・南陽市長
今回、「持続可能な地域社会の実現と流域治水の推進」と「命を守る避難情報の発信と防災DXによる効率的な災害対応の実現」という二つのテーマを設定した。一つ目は、まちづくりと防災をいかに効果的、効率的に掛け合わせて、自治体運営を行っていくかという観点で、もう一つは人口減少が進展し、自治体職員も十分に確保できない中で、防災DXの推進は必要不可欠となっているという意味がある。このテーマの議論が今後、流域治水の推進や住民の被害防止、減災に少しでも役立つことを心から願っている。
■第1部・持続可能な地域社会の実現と流域治水の推進
「ながす・ためる・ひかえる」 奈良県川西町
小沢町長 2017年の台風で農地の半分以上が浸水する被害を受けた。豪雨の際には、町の北を蛇行する大和川に水が集まるため、浸水被害を軽減する3本柱「ながす・ためる・ひかえる」を実践している。豪雨前には、住民の協力でため池と井堰(いせき)の水位を下げている。
町では、川が合流し、浸水が多い地域を「治水のためのエリア」と位置づけた。工業団地を整備する際には、必要な「開発調整池」以外に「内水調整池」を造り、河川の氾濫を防いでいる。
また、大和川の増水時に河川の水を貯留する(コンクリート構造の)保田遊水地が完成した。治水機能を持つ一方、平常時は地域活性化の拠点として活用。国内初の国際規格インラインスピードスケート場や、3人制バスケットボールコートを整備し、「オーバルパークかわにし」として開園する予定だ。
昨年、地権者の協力を得て、町内の農地が全国初の「貯留機能保全区域」に指定された。貯水機能を持つ農地を恒久的に保持することで、周辺の浸水被害抑制が期待されている。
LINEでデジタル水防 愛媛県大洲市
二宮市長 肱(ひじ)川(かわ)は、豪雨の際に474本の支流からの水が流域中心部にある大洲盆地に流れ、洪水によって水がたまりやすい土地で、治水が難しい。2018年の豪雨による浸水被害は近年最大規模で、5人が亡くなった。この水害を受け、国・県・市による緊急治水対策「つなごう肱川プロジェクト」が発足し、堤防やダムなどを3段階で整備する計画だ。肱川水系都谷川は、四国初の特定都市河川に指定され、国の事業として「都谷川排水機場」を整備する予定になっている。
18年の豪雨では、被害が大きかった三善地区で人的被害がなかった。「災害・避難カード」を作り、顔の見える関係作りと避難を促す共助の取り組みを進めてきたからだと思う。
流域自治体の消防団では、LINEを活用した全国初「デジタル水防」を導入し、消防団員が現場で被災状況や位置情報を共有できるようになった。また、肱川沿いを活性化する「かわまちづくり」にも取り組んでいる。「しろしたかわみなと」では、マルシェなどのイベントを開催し、川に親しむ機会を創出している。

オリジナル浸水マップ 高知県いの町
池田町長 仁淀川が縦断する地形から水害が多発しており、2040年までに水害犠牲者ゼロを目指して、「氾濫を減らす」「備えて住む」「安全に逃げる」の三つの対策を推進している。家庭からの治水として雨水浸透ますや貯留タンクの設置補助を行う一方で、活用実績が少ないため広報活動を強化する方針だ。
22年度には立地適正化計画を策定し、居住誘導区域を設定。高台移転が難しい地域では、家屋補強を条件に垂直避難可能な家屋を居住誘導区域とするなど、地域の実情に合わせた対策を講じている。最新技術の導入も積極的に行っており、3D都市モデルを活用した浸水シミュレーションを公開。町内13カ所に浸水深表示板を設置し、「ワンコイン浸水センサ」も導入した。
宇治川流域の自主防災会連合会と連携し、浸水リスクを調査したオリジナル浸水マップを作製。マップは住民研修会で活用し、社会福祉施設と連携した避難訓練を実施。また、堤防強化や掘削に関する研修会も開催するなど、行政と地域住民が一体となって防災力向上を図っている。

◆意見交換 ――川に親しみ意識高める
伊藤・桑名市長 日本最大の海抜ゼロメートル地帯(海面より低い場所)に位置する。伊勢湾台風(1959年)後、堤防が整備された。南海トラフ地震の津波想定エリアに指定された場所に消防本部があったが、今年、高台に移転した。
小中学校を再編し、小中一貫校を整備しているが、現学校は標高が低い場所にあるため、住民と議論し、安全な場所に新しい学校をつくることになった。来年、標高約40メートルの場所に開校する予定だ。
伊東・倉敷市長 昨年、南海トラフ地震の臨時情報が出た。一人で逃げられない避難行動要支援者に対し、自治体は個別の避難計画を作る努力義務があるが、作っていない人も多かった。
市職員が、2時間で最大3メートルの津波が来る地域の避難行動要支援者約600人の自宅を2日間で回り、うち約230人の個別避難計画を作成。その後、昨年度末までに浸水想定区域外の避難行動要支援者も含めて約1830人の個別避難計画を作った。民生委員とも連携し、さらに進める。
黒須・角田市長 「暴れ川」である阿武隈川が流れるが、堤防がそびえ、「川が危険」という意識が育ちにくい。2019年台風の後、阿武隈川水系の河川が特定都市河川に指定され、流域治水対策が進むが、大洲市の肱(ひじ)川(かわ)のように、川に親しみを持つ視点を参考にしたい。川西町では、治水に関する勉強会を開いているのか、工業団地に企業が積極的に入居しているのかも聞きたい。
小沢・川西町長 自治会長の集まりで治水に関する話を共有し、町全体の意識が高まっている。工業団地については、大阪と名古屋をつなぐ高速道路が近い立地が強みだ。治水に取り組む町であることをアピールし、かさ上げした上で分譲していることが、企業の購入につながっている。
染谷・島田市長 避難指示を出しても、住民の0・03%程度しか避難所に避難しない。市では、区域を指定して避難指示を出している。本当に危険な時に逃げてほしいからだ。一方で、住民から「隣町は避難指示が出ているが、市はまだ出さないのか」との指摘も届く。被災地域がどの段階で避難指示を出したかを知りたい。
国定・国交政務官 九州の自治体では、朝から防災無線を通じて、「運動会を中止します」などの情報を細かく伝え続けた。その結果、住民の危機意識が高まり、避難指示を発令した段階で、通常より人が動いた。また、SNS(交流サイト)が発達する中で、信頼する「誰か」が情報を発信することが、住民の避難行動にプラスに働くと言われる。避難情報発令のありようを考える段階にある。
長谷川・菊川市長 市を流れる菊川は、全国一短い1級河川だ。19年台風で最初に菊川支流の牛渕川が越水したことから、河道掘削を国が進めた。その後も豪雨に見舞われたが、越水していない。今年、菊川水系黒沢川が特定都市河川に指定された。DXなど新しい取り組みは菊川でまず検証してほしい。
稲田・見附市長 市は信濃川下流域の上流部にある。迅速に住民が避難できるようにSNSを活用して情報発信しているが、消防団の力を借りる「デジタル水防」(大洲市)が興味深い。開発経緯を教えてほしい。
二宮・大洲市長 LINEを活用した「デジタル水防」は消防団長の提案。団員所有の各スマートフォンを活用することで、現場の状況がリアルタイムで分かる。23年の林野火災でも活用した。
湊・由利本荘市長 昨年、線状降水帯による豪雨があった。国交省の事務所長から、水位の状況などの連絡がある中で避難指示を出すことができ、心強かった。防災行政無線を通じて住民に避難指示を出したが、雨音で聞こえにくい。LINEも配信したが、高齢者の多くは使えないため、一斉に自宅の固定電話やファクスを通じて知らせる仕組みを作った。
松浦・三朝町長 23年台風で、豪雨が降った。町は山が9割を占める。砂防ダムが土砂災害の被害拡大を食い止めたと考える。町の山は険しく、下流域に他市町がある。できるだけ開発せず、山の機能を生かしたい。高齢者避難指示を出した後、地域ごとにバスを出し、明るい時間帯に避難を促している。
大鷹・日高町長 町を流れる川の河川敷に公園がある。河川整備とともに、河川敷に観光施設を設置するなど地域活性化策も検討しており、大洲市の川に親しむ取り組みを詳しく聞きたい。
二宮・大洲市長 国交省と相談し、河川敷を活用した公園を、イベントなどでも使えるようにした。一部はグラウンドとして活用。一部の堤防を階段状にして眺望のよいスペースにし、川の景色を楽しんだり、花火大会を見たりできるようにしている。
細川・幌加内町長 雨竜川流域で、北海道開発局が、ダムのかさ上げと洪水調節機能事業などに取り組んでいる。絶滅危惧種の淡水魚「イトウ」がダムに生息することを生かした地域活性化を目指し、今年「雨竜川の流域一体整備における地域共創検討会」が発足した。
■第2部・命を守る避難情報の発信と防災DXによる効率的な災害対応の実現
町内に「浸水センサ」 山形県中山町
佐藤町長 最上川と須川の合流地点にある中山町は歴史的に水害が多く、近年では3回避難情報を発令している。また住民の7割以上が浸水想定区域内に居住し、対策が急務だ。
3月には「石子沢川流域水害対策計画」を策定した。河道内堆積(たいせき)土砂の撤去といった氾濫をできるだけ防ぐための対策から、切れ目のない防災教育など被害を軽減させるための施策まで、幅広く定められている。
防災DXに関しては、統合型GIS(地理情報システム)や町の公式LINE、個別避難計画の作成や管理をスムーズに行うためのアプリケーションなどの導入を進めている。また、米宇宙開発企業スペースXが提供する衛星インターネットサービス「スターリンク」も導入予定だ。町の防災訓練では、ドローンによる情報収集訓練も行っており、災害時にも情報を途絶えさせず、発信していく。
国土交通省の事業「ワンコイン浸水センサ実証実験」では、町内計6カ所に「浸水センサ」を設置した。リアルタイムで確認し、浸水情報を受信したらすぐに防災情報として発信する。
「水の学習会」を拡大 兵庫県西脇市

片山市長 2004年の豪雨で約320億円の被害が出た。ハードとソフト両面で対策を進め、18年は総雨量が1・6倍となる豪雨が発生したが、浸水戸数を97%減らすことができた。
まずハード面では16年に国、県、近隣の加東市とともに「加古川中流部河川整備推進協議会」を発足させ、密に情報共有を行いつつ、治水整備を推進した。
ソフト面では、04年の豪雨以降、福地地区で開催されていた「水の学習会」を他の地域に拡大。流域治水の観点から流域合同で実施することにより、各地区の課題を共有してもらえた。
このほか、気象予報士と防災士の資格を持つキャスターの澤麻美さんを講師に迎え、ワークショップを開催した。住民それぞれがマイ・タイムラインを作り、適切な避難行動について検討した。
さらに、井堰(いせき)ポンプの停止や雨水排水ゲートの操作を地元の町内会にお願いすることにした。全体の管理は市が行い、ゲリラ豪雨などの緊急時は地元住民がスマートフォンで遠隔操作することで、迅速な対応が可能になった。
◆意見交換 ――迅速・的確な発信必要

泉谷・珠洲市長 能登半島地震に続き、昨年9月に発生した豪雨では市内のいたるところで川が氾濫し、土砂災害の被害が大きかった。逃げ遅れた住民もおり、防災DXを推進して、より効果的に情報発信をすることの重要性を再認識した。そこで、市の公式LINEに防災情報を発信できるアプリケーションを開発した。どこにいても、ハザードマップに基づいたリスクが分かり、水位計の数値もリアルタイムで見ることができる。
坂口・輪島市長 能登半島地震への対応で水害対策が十分に取れない中、昨年9月の豪雨災害が発生した。普段は河川の状況を見ながら避難指示の発令を検討するが、今回は地震の影響もあったので、すぐに発令した。防災行政無線、市の公式LINEなどで避難を呼びかけたが、それを知らない市民もおり、避難行動に結びつける難しさを感じた。DXを活用して、情報発信を強化していきたい。
高橋・村上市長 村上市では空振りをおそれず、すぐに避難指示を出すようにしてきた。市民も慣れてきたのか、迅速に避難してくれるようになった。災害時には公的機関、報道機関、SNS(交流サイト)などさまざまな情報源からのニュースが錯綜(さくそう)し、タイムラグもある。どうしたら市民が適切に情報を受け取れるのか、メディアの視点からも示唆をいただきたい。
神達・常総市長 2015年9月に線状降水帯による大雨があり、鬼怒川堤防が決壊して市内の3分の1が浸水した。以降、市内29カ所の指定避難所の開設・混雑状況を確認できるシステムの活用など、さまざまな取り組みを行ってきた。現在、市内の中学生とつくば市の研究所とともに、中学生が家族や近隣住民にどう呼びかければ避難行動に結びつけることができるか、共同研究を行っている。
加藤・戸沢村長 昨年7月、山形県と秋田県で記録的な豪雨が発生し、戸沢村蔵岡地区付近で最上川中流が氾濫した。周囲の集落が水没して孤立し、最大で約3メートル浸水した。恵みを受けてきた最上川に牙をむかれることは、誰も想像していなかったと思う。水害後に蔵岡地区の69戸を集団移転する決断をし、取り組みを進めている。
山科・新庄市長 新庄市では、最上川中流地域にある一部集落の移転が20年に完了していたので、昨年7月の豪雨は被害を免れることができた。ただ、今も市内での内水や最上川が氾濫する危険性があるため、一時的に田んぼに雨水をためることで民家の浸水などの低減を図る「田んぼダム」の整備計画を立て始めた。流域治水について考える際は、農業などを含め幅広く考えていかなければいけないと感じる。
草地・磐田市長 磐田市では台風に伴う豪雨で22、23年と2年連続で敷地川の堤防が決壊した。復旧作業が進められているが、全国的に土木職員が少なくなっているので、専門知識を有する人材をどう育てていくか、国をあげて対策する必要があるのではないか。また、身近な川について知らない住民も多いと感じた。「自分たちの街の川がどのように流れているか」「どのタイミングで避難指示を出しているか」などを職員と私の質疑応答形式にして、ユーチューブで配信した。市外に住んでいる親戚が市民に情報を伝えてくれることもあるので、SNSでの発信も重要だ。
首長の経験共有、有意義
中野洋昌 国交相・水循環政策担当相・国際園芸博覧会担当相

このサミットは2004年の福井豪雨、新潟福島豪雨、台風23号による激甚な水害を契機に、05年から被災自治体の首長が発起人となって開催されており、各地域における防災力の向上、そして意識づけに大きく貢献している。昨年1月1日、最大震度7を記録する地震が能登半島を襲い、さらに9月にはその復旧復興の途上にあった被災地が、また大雨に見舞われた。
他にも記録的な大雨によって、全国各地で浸水被害や土砂災害が発生するなど、近年災害は激甚化、頻発化し、地域住民の生活や経済活動に大きな影響を及ぼしている。
こうした状況に対応するために、流域の上流から下流まで、あらゆる関係者が共同して治水を行う流域治水の取り組みをより一層強力に推進していくことが重要だ。現場の最前線で流域治水に取り組んでいる市町村長の経験と知恵を全国に発信することは、大変有意義なことで、その貴重な意見を今後の国土交通行政にしっかり反映させていきたい。
国交省としても、これまで培ってきたインフラ整備や管理に関する知見や地方整備局の現場力、技術力を生かして、事前防災対策を含めた流域治水の着実な実行とさらなる充実を図り、地方自治体をサポートしていきたい。
異常気象は今や「日常」
元村有希子・毎日新聞客員編集委員
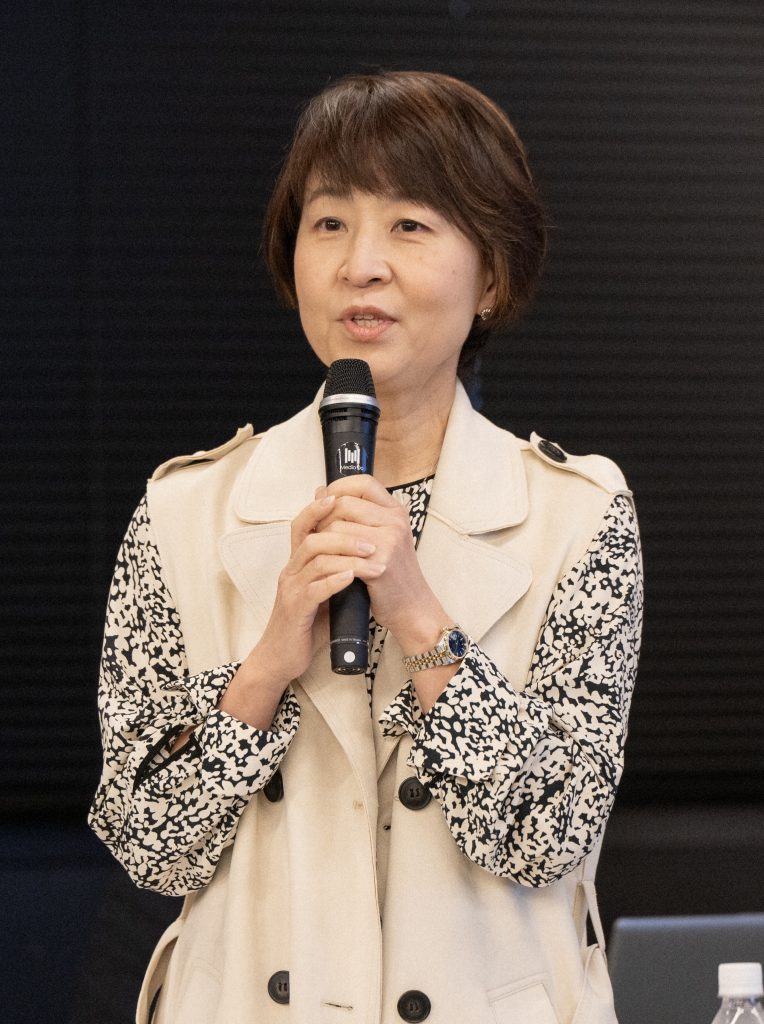
20回目のサミットは、最大震度7の地震からの復興の途上、豪雨による水害に見舞われた能登半島の輪島市、珠洲市など10自治体が初参加した。
会場は少し違う空気に包まれていたように思う。気候変動の影響で、異常気象は「日常」になりつつある。水防を含めたインフラが老朽化し、苦しい財政状況の中、優先順位をつけて対処しなければならない。過疎化、高齢化も進み、スムーズな避難が年々難しくなっている。水防に関わる人手不足も加速している。
こうした困難にどう立ち向かうか。参加自治体は同じ問題意識を共有している。民間の資金力をうまく組み込んだ対策や、人手不足を補うDX事例の発表に、他自治体から次々と質問や追加の事例発表が相次いだのは、象徴的だった。
首長の皆さんの使命は、住民一人一人の命を守ること。これに尽きる。一方マスメディアは、各自治体の困難や成功体験を報道することで、間接的に協力できる。
災害は起きてからでは遅い。日ごろから災害の怖さを自覚し、自分なりに考え、備え、いざという時に行動に移せる事前防災力を高めることが必要だ。自治体の「虫の目」と、メディアの「鳥の目」の共同作業を通して、実現に貢献したいと改めて感じた。
事前防災の重要性増した
国定勇人・国交政務官
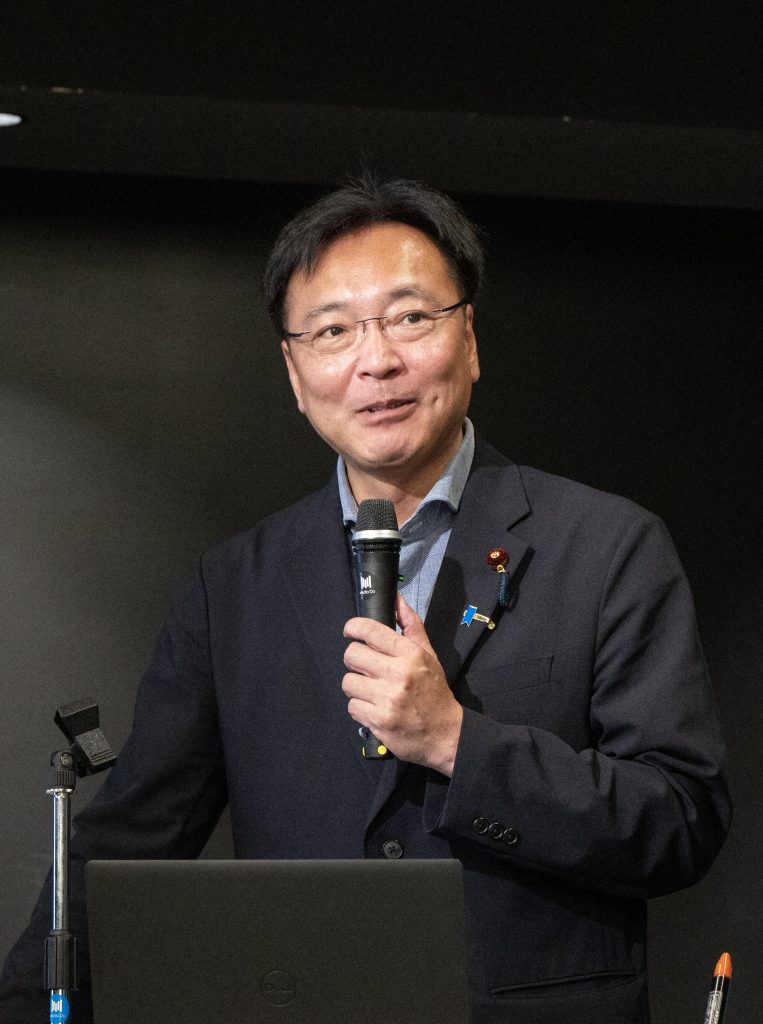
新潟県三条市長として、13年間水害サミットに参加していたが、議論が深掘りされ、ハード整備はもちろん、事前防災の重要性が増していると感じる。流域治水についても多くの首長が言及しており、心強く思う。国土強靱(きょうじん)化実施中期計画では、今後5年間で20兆円強の予算が打ち出されており、しっかりと取り組んでいきたい。
ソフト面では、情報把握の強化や情報発信手段の複数化が進んでいる。「ワンコイン浸水センサ」の活用など、自治体の積極的な取り組みに感銘を受けた。しかし、行動変容につながる情報発信や、避難行動要支援者への個別支援といった新たな課題も浮上している。
これらの課題については、水害サミットで議論を深め、実践の度合いを高めていく必要がある。国交省としても、内閣府防災等と連携しながらバックアップしたい。
最後に、気象防災アドバイザー制度を紹介する。気象庁OBなどのノウハウを各市町村で活用する制度であり、詳細な気象予測は、避難情報の発令に非常に役立つ。私自身も三条市長時代に活用し、大変助かった。
この制度も活用しながら、一人も犠牲者を出さない、生命のみならず財産も守り切るという精神で、国交省として皆様方を支えたいと考えている。
自治体参加者
泉谷満寿裕・石川県珠洲市長
坂口茂・石川県輪島市長
高橋邦芳・新潟県村上市長
稲田亮・新潟県見附市長
早川尚秀・栃木県足利市長
神達岳志・茨城県常総市長
加藤文明・山形県戸沢村長
佐藤俊晴・山形県中山町長
白岩孝夫・山形県南陽市長
山科朝則・山形県新庄市長
矢口明子・山形県酒田市長
湊貴信・秋田県由利本荘市長
黒須貫・宮城県角田市長
大鷹千秋・北海道日高町長
細川雅弘・北海道幌加内町長
日高利夫・宮崎県国富町長
服部浩治・大分県日田市副市長
権藤英樹・福岡県うきは市長
池田牧子・高知県いの町長
二宮隆久・愛媛県大洲市長
伊東香織・岡山県倉敷市長
松浦弘幸・鳥取県三朝町長
高江啓史・奈良県田原本町長
小沢晃広・奈良県川西町長
片山象三・兵庫県西脇市長
門間雄司・兵庫県豊岡市長
伊藤徳宇・三重県桑名市長
長谷川寛彦・静岡県菊川市長
草地博昭・静岡県磐田市長
染谷絹代・静岡県島田市長
<自治体以外の参加者>
国土交通省=中野洋昌国交相・水循環政策担当相・国際園芸博覧会担当相、国定勇人国交政務官、藤巻浩之水管理・国土保全局長(肩書はサミット当日)
毎日新聞社=元村有希子客員編集委員
※水害サミットは、公益財団法人河川財団の河川基金の助成を受けて開催された。