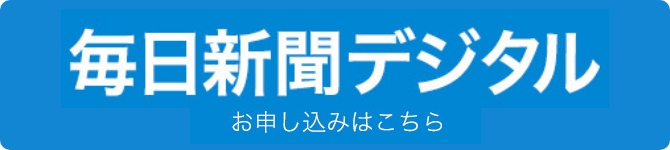2025.10.07
地図が読めなくても 外国語で万博会場案内 できることに自信

大阪・関西万博の会場で接客のボランティアをした木村朱美(あけみ)さん(62)=大阪府枚方市。自らは視覚障害があり、地図を頼りに道案内はできないものの、イタリア語や英語で入場者らをもてなした。万博を通じて気づいたことを語った。
苦手なことを補い合う
大阪・関西万博の会場内で接客のボランティアを務めました。私は目が見えないので地図は読めませんが、英語やイタリア語で伝えることはできます。一方、外国語はできなくても地図を読める晴眼者の仲間がいます。お互いに得意なことを生かし、苦手なことを補い合えばいい。最先端の技術が並んだ万博でも、人と人との連帯の大切さを感じました。
私は35歳のころ、網膜色素変性症を発症しました。徐々に視野が狭くなったり視力が低下したりする難病です。10年ほどで白杖(はくじょう)が手放せなくなり、今では光を感じられる程度です。
1970年の大阪万博には、家族で何度も通いました。笑顔で応対するコンパニオンの姿を覚えています。テレビや本でしか見たことがなかった遠い国を直接感じたことで、外国に興味を持ちました。大学時代にイタリアに1年間留学し、イタリア語と英語を習得しました。帰国して、旅行会社に入りました。
万博が55年ぶりに地元・大阪にやってくることになりましたが、年齢や視覚障害があることからコンパニオンは無理だろうと思いました。でもボランティアならできるかもしれないと思い切って応募しました。当選した時は、小躍りしてしまいました。
4月の開幕以降、10回ほど会場内で活動しました。「ENGLISH」「Italiano」というバッジを着けていて、英語やイタリア語で話しかけられたこともありました。
AIにはない おもてなしの心
ボランティアは6人ほどのグループで活動し、主に、道案内や記念写真のお手伝いをします。同行してもらっている介助者の松永朋子さん(54)が、お客さんのスマートフォンで写真を撮ります。大屋根「リング」を背景に入れるために、松永さんがしゃがむことがあるのですが、私は松永さんの肩に手を置いて、タイミングを合わせます。シャッターを切る時は、「笑顔で」と声を出しています。
おもてなしの心や、人に寄り添おうとする気持ちは、まだまだ人工知能(AI)には備わっていないように思います。だからこそ、まだまだ人間がボランティアとして活動する意義があると感じています。
配慮が「バリアー」にもなる
障害者に失礼にあたると考えている人が多いからか、周りから障害の程度を聞かれることは、あまりありません。配慮してもらっていると思うのですが、「バリアー」になっている面もあります。何か行動するには、私の側から、できることやできないことを伝えることで「バリアー」を破る必要があるのです。
普段の生活では、人の手を借りることも多いですが、自分が頑張る姿を見せることで、誰かに「助けてあげよう」と思ってもらえるよう努めてきました。
そんな心境にも変化がありました。万博のボランティア活動を通じて、目が見えなくても、自分にできることがあると実感しました。だからこそ、できないことをはっきり言って、周りの人の助けを求めるようになれたと思います。自信がついて、少し心が強くなったのでしょう。これからもチャレンジをして、人生を楽しみたいです。【聞き手・高良駿輔】
きむら・あけみ
1962年、大阪府生まれ。大学卒業後、旅行会社に就職。35歳で網膜色素変性症を発症し、徐々に視力を失った。現在は会議の録音を文字に起こす仕事をしている。
関連記事