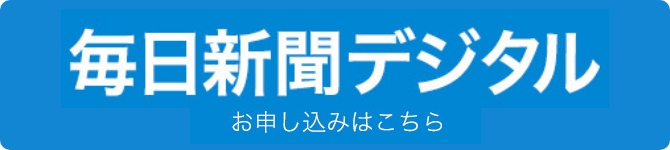2025.07.13
目立つ外国人の水難事故 「深い、速い、滑る」にリスク 対策は?

スウェーデン9割、日本6割、ベトナム4割、ネパール2割。この数字は何だと思いますか――。
猛暑のシーズンを迎え、各地で水の事故が相次いでいる。
最近は在留労働者やインバウンド(訪日外国人客)の増加に伴い、外国人の水難事故が目立つ。自治体などでは、文化や習慣の違いを踏まえた対策を模索している。
「海がないので遊んでみたい」
千葉県九十九里町の片貝海岸で6月、ベトナム人男性2人が流され、福井県敦賀市の海岸でも海水浴に来ていたミャンマー人男性が溺れて亡くなった。
「日本財団海のそなえプロジェクト」の調査によると、2024年夏(7月1日~8月31日)に報道された水難事故は229件265人で、うち172人が死亡した。
おぼれた人の約1割が外国人で、場所は河川が半数弱、海が4割程度だった。遊泳禁止区域など、安全管理が行き届かない場所での事故もあった。
日本の水辺のルールを理解していないケースもあるが、それだけではない。
経済協力開発機構(OECD)は、各国の自力で泳げる15歳以上の割合(19年)を発表している。それが冒頭の数字だ。
スウェーデンを筆頭に北欧諸国やオランダが9割に達している一方で、アフリカ、アジアは総じて低い。日本は60%台だ。
在留者に多い出身地をみると、タイ50%台▽ベトナム・フィリピン・インドネシア40%台▽ミャンマー・インド30%台▽中国・ネパール20%台――となっている。
学校教育の普及度やプールなどの設備、水に親しむ場所があるかといった自然環境が影響しているとみられる。
6月にネパールから来日したばかりの名古屋市のカフェ店員、ビクラムさん(30)は「自分は川で泳いだことはあるが、みんなが泳ぐわけではない」と話す。「ネパールは海がないので日本の海で遊んでみたい」と目を輝かせた。
水泳経験の少ない人が慣れない土地で泳ぐのはリスクを伴う。加えて日本特有の地形や自然がある。川は流れが複雑で急流があり、大陸のゆったりした流れとは異なる。
川遊びのスポットが多い岐阜県では24年、7人の外国人が水難事故で亡くなった。これを受け県は「深い」「速い」「滑る」など日本の川の特徴や注意点を記した6カ国語のチラシを作製した。
今夏は外国人を雇用する企業や多文化共生ボランティア、防災リーダーらに依頼し、注意事項の周知を進めている。県外国人活躍・共生社会推進課は「内容を確実に伝えるため、外国人と直接つながりがある人に橋渡し役になってもらった」と話す。
「浮いて待て」
では、泳ぎに慣れない人が安全に遊ぶにはどんな点に気を付けたらいいのか。
水難学会理事を務める長岡技術科学大大学院の斎藤秀俊教授は「川も海も、入る前に深さを確認すること」と指摘する。
外国人の事故では、川の透明度が高いからと駆け寄ってそのまま飛び込み、深みで溺死するケースがよくあるという。
海の場合は、同じ場所でも波が寄せると深くなる点が要注意だ。川も海も遊ぶ際は「ひざ下の深さまで」とアドバイスする。
斎藤教授が、命を守るのに最も重要だと力説するのが「浮いて待て」だ。
水に落ちたり流されそうになったりした時に焦って泳ごうとせず、あおむけに浮いたまま助けを待つ方法だという。「泳げなくても大丈夫、むしろ泳がない方がいい」と説明する。
国内では安全教育の一環として、着衣水泳と合わせて小学校などで広く指導されている。
水難学会は11年から、東南アジアの国々で「浮いて待て」の普及活動を始めた。相次ぐ水害から身を守るのが狙いだ。
フィリピン、タイ、インドネシアなどで教室を開く。子どもだけでなく、大人のスイミングスクールなどでも実施している。
斎藤教授は「こうした教育を受けた人が増えていけば、たとえ泳げなくても命を落とす事故は減っていく。地道にやっていくしかない」と話す。
国によって教育や文化、自然環境は大きく異なる。さまざまなリスクを「日本だから当たり前」とせず、丁寧に情報を伝えていくことが大切だ。【太田敦子】
関連記事