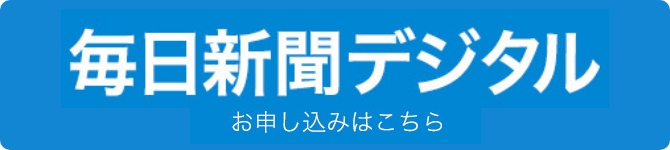2025.09.12
釧路計画地で確認のキタサンショウウオ 場所移しても定着は困難

北海道の釧路湿原国立公園に近い市街化調整区域で太陽光パネルの設置が相次いでいる問題で、国立公園内にある国史跡「北斗遺跡」南側の湿原で、釧路市の天然記念物「キタサンショウウオ」の幼生が生息していることが、湿原の学術調査に取り組む「北方環境研究所」(神田房行所長)の調査で確認された。
キタサンショウウオは、北海道・釧路湿原を象徴する両生類の一種だが、生息適地の大部分は国立公園外の市街化調整区域にある。開発の脅威にさらされ、「既に生息地の3割が消失した」と推定している学術論文もある。
希少種を守るための環境保全措置としては、一般的に「回避」「低減」「代償」のいずれかの方法がとられる。太陽光パネルの設置場所を一部変更する「回避」、地下水位などを考慮して工事の影響を少なくする「低減」で保全が図られた事例は少数ある。
一方、キタサンショウウオの卵のうや成体を別の場所に移動する「代償」も行われてきたが、保全の効果は長年疑問視されていた。
キタサンショウウオを研究するNPO法人「環境把握推進ネットワーク」の照井滋晴理事長がその効果を検証したところ、定着は難しいことが判明した。
釧路市教育委員会が1991年~2019年、移植先の環境で卵のうが定着するかどうかモニタリング調査を実施。移植されたのは、卵のう2301対(一対には約200個の卵が入っている)と成体268個体。移植初期は定着しそうな結果が出ていたが、その後の卵のう数は上下しながら減少が続き、07年以降は産卵が確認できなくなった。
このため照井さんは「移植によって保全を図るのは困難」と判断した。【本間浩昭】
関連記事